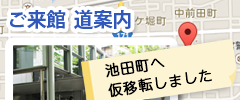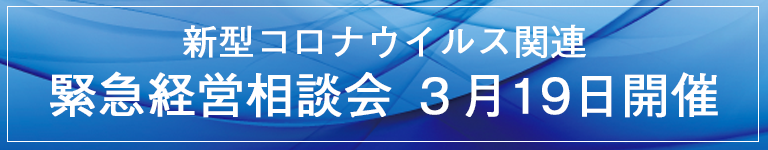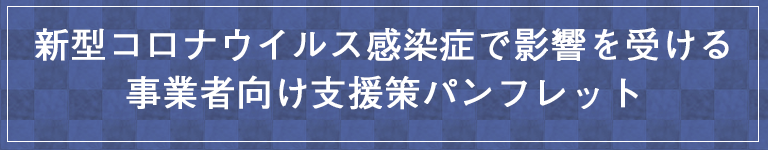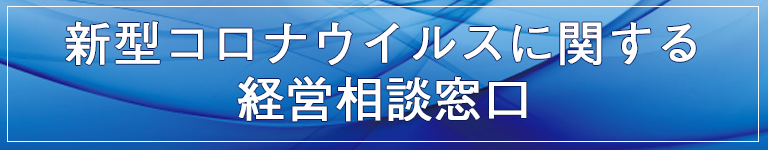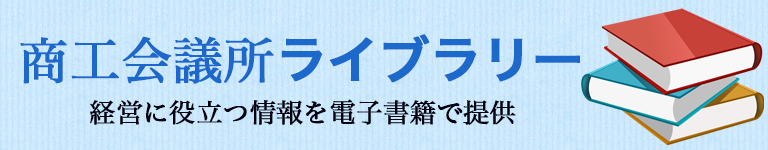株式会社山村製壜所

ガラスびんのファンづくり
 リサイクルの優等生といわれるガラスびん。
リサイクルの優等生といわれるガラスびん。
洗って繰り返し使うだけでなく、砕いてびんの原料として再利用すれば、ゴミを出すことのない環境に優しい製品だ。
こうしたガラスびんの特性を知ってもらおうと、山村製壜所では市内の小学生に出前授業を行っている。行政、NPO法人「こども環境活動支援協会(LEAF)」、企業、PTAが中心となって市内の小学生に環境への取り組みを教える活動の一環だ。
西宮市内には、「ガラスびん会社」「金型会社」「酒造会社」、「カレット会社」、「ポリケース会社」の5社が集積している。山村製壜所は、珪砂という砂や石灰石などの天然資源と、空きびんを砕いた※ カレットを溶かして、日本酒や化粧品の容器を始めとするさまざまなガラスびんを製造している。
出前授業では、その5社のブースを生徒たちが順にまわれば、資源を無駄にせずに循環していく「ガラスびんの一生」が分かる仕組みになっている。
山村製壜所のブースでは、段ボールで作った溶解炉を通ったり、びんの金型にはさまれたりして、びんが出来るまでの工程を体感できる。社員が作った素朴なものだが、子ども達には大人気で、ブースが置かれた体育館には「もう一回」という子ども達の声がひびく。
こうした出前授業を年間2、3回行うほか、工場見学も受け入れている。こうした授業では、「ガラスびんに対する思い入れが強く、出前授業はライフワークだと思っている」という山村昇社長みずからが熱弁をふるう。子どもだけでなく、PTAのおかあさんや先生にも「ガラスびんのファンになってもらいたい」という思いが伝わる授業だ。
山村グループとしていち早くリサイクルを提唱
 山村社長が啓蒙活動に力を入れるのには、わけがある。
山村社長が啓蒙活動に力を入れるのには、わけがある。
山村製壜所の親会社、日本山村硝子がガラスびんのリサイクルを開始したのは、1972年。「消費こそが美徳」という風潮の中で、当時、社長だった山村社長の父が、「資源のない日本のメーカーがモノをつくるだけでなく、回収して資源の使用を抑制しなければ日本はだめになる」と、小学生だった山村社長にも力説していた。
「リサイクル」を提唱する山村社長の父は、人から自転車(サイクリング)を趣味にしているのかと聞かれた、という笑い話もあるぐらい、まだ一般的にはリサイクルは認知されていなかった。社内でも反対意見があったが、事業部を立ち上げ、いち早くびんの回収システムを構築した。
CO2を大幅に削減
リサイクルに対する強い思いを受け継ぎ、山村製壜所も製造工程で出た不良品は砕いて色別に分類し、カレットとして再利用している。
また、2005年には、ガラスの溶解炉の燃料を全面的に重油からガスに切り替えた。「環境に優しいガラス」を標榜しながら、重油を燃やしているのは矛盾している。
山村社長は、「次の炉の補修時には、ガスに切り替えよう」と2002年の社長就任時から決めていたという。炉の全面ガス化により、CO2が約20%削減できた。今年8月にもう一つの炉の補修が終わり、こちらも約15%の省エネが実現した。
こうした経営面での努力と啓蒙活動の両輪で、「循環型社会」の形成に貢献しようとしている。
※ カレット・・・ガラス製品をリサイクルする際に、いったん破砕した状態の「ガラス屑」のこと。
株式会社山村製壜所
- 代表取締役社長:山村昇
- 資本金:5,000万円
- 社員数:25名
- 本社:西宮市鳴尾浜2-1-18
- TEL:0798-43-1301
- https://www.yamamura.co.jp/yamabin/

 0798-33-1131
0798-33-1131