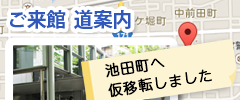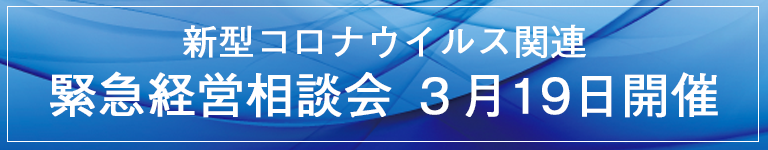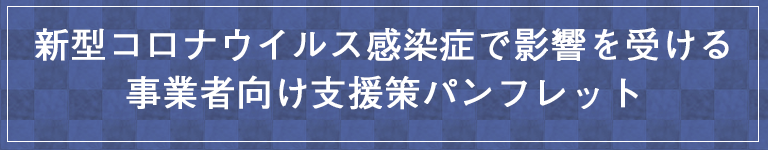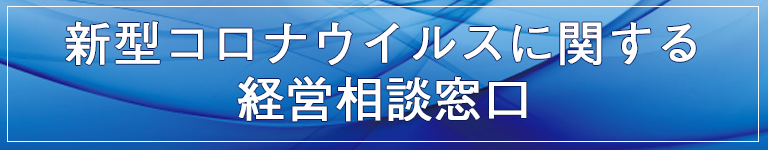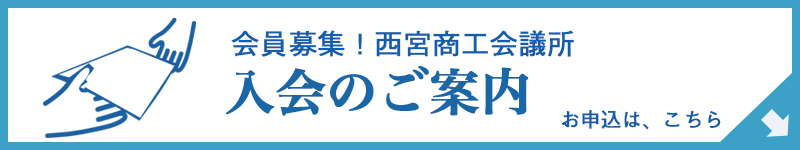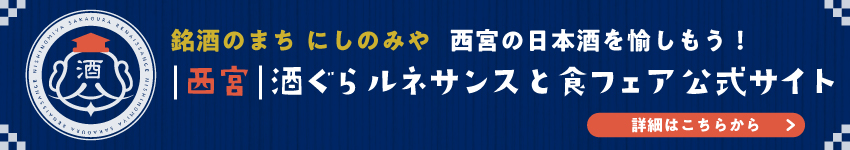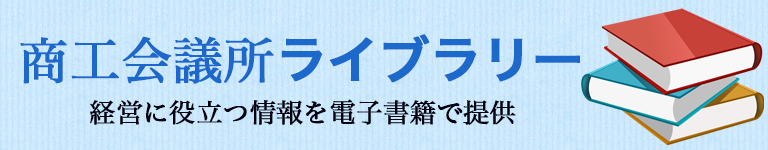事業承継対策【2】/株式支配力
(1)株式支配力と事業承継(株式支配力を維持する前提での事業承継)
株式支配の安定を考慮せず、相続税対策を行うのは比較的簡単な話となります。株式を安く購入しても課税上弊害がない立場の人に株式を安い価額で譲渡すれば、高い評価額の株式が株式譲渡の対価として受取る金銭に置換わることになります。
株式という財産は一物一家ではなく、支配力の有無によって全く違った評価となります。株式評価方法の詳細は後述しますが、株式支配力が高い株主は高い評価額(原則評価)が適用され、株式支配力が低い株主は低い評価額(例外評価)が適用されることになります。
この株式支配力が低く、安い株価が適用される株主の代表的な例は次のとおりです。
- 従業員
- 取引先企業
- 遠縁の親族・血族
目の前に迫る相続税負担が大きいと、どうしても相続税を節減するために、株式は上記の安い株価が適用される株主に分散が進む傾向となります。
その結果、驚くほど多くの会社の株主構成において前述の少数株主に広く株式が分散されてしまっています。
株式が分散されますと、次のような弊害が生じます。
- ① 従業員持株
- 会社経営は順調な場合だけとは限りません。業績が悪い場合には、仕方なく人件費の圧縮を図る必要も生じます。
この時、従業員の持株が多い場合、従業員の給与をカットする前に、従業員が株主として経営者の経営責任を問うというプレッシャーがかかるため、大胆な経営革新の断行の阻害要因となってしまいます。 - ② 取引先企業持株
- 取引先が会社株式を所有する場合、安定的な取引関係が続けば良いのですが、例えば購買業務の合理化のため1社購買を複数社購買に切り替えようとする際、既存の取引先が当社の株主であれば、遠慮が働いてしまいます。また、得意先が倒産してしまう場合、当社の株式が良からぬ債権者に渡ってしまうリスクも生じます。
- ③ 同族内分散株式
- 近い仲ほど金銭面でトラブルが生じますと、感情が絡んでしまうので、果てしなく泥沼の抗争が繰り広げられるおそれがあります。こうした無用の争いを避けるために株式を所有する親族に役員報酬等を支給する会社も多いのですが、これは法人税上リスクのある取引ですし、だから言って急に取り止めようとしても株式を持たれている手前簡単には話を切り出すことができません。
- ④ 株式買取請求
- 会社は株主から常に株式の買取りを求められるリスクを抱えています。
合併等組織的な行為を実施する場合には法的根拠をもった株式買取請求権のリスクがありますが、そうした法的根拠の背景が無くても、単に「金に困っているので株式を買取って欲しい」と求められれば、無碍に断る訳にもいかないでしょう。
最近でこそ上場会社において会社買収の事例が目立つようになりましたが、世間一般では昔からこのような事例は驚くほど多く発生しています。
このように、株式が分散しますと会社経営には多大なる悪影響を与えます。
未だ株式が分散していない会社は極力株式が分散しないように、既に株式が分散してしまった会社では分散した株式の弊害をいかに取り除くか、検討する必要があります。
(2)分散株式の対策(分散は容易でも、集中は困難)
水は高いところから、低い方へしか流れません。株式も同様に支配力が強い立場から、弱い立場へは分散し易いのですが、逆に分散した株式を支配力の強い株主が買い集めようとするのは極めて困難です。
- <株式売買における課税関係>
- ○ 個人 → 個人
- 売主 「対価」が収入金額になる
- 買主 「時価」と「対価」の差額は贈与税課税
- ○ 法人 → 個人
- 売主 「時価」と「対価」の差額は法人税課税
寄付金(賞与) ****
/ 売却益 **** - 買主 「時価」と「対価」の差額は所得税課税
一時所得または給与所得
- 売主 「時価」と「対価」の差額は法人税課税
- ○ 個人 → 法人
- 売主 1) 低額譲渡(「時価」の1/2未満)の場合
「時価」での譲渡とみなして所得税課税
2) その他の場合
「対価」が収入金額になる - 買主 「時価」と「対価」の差額は法人税課税
有価証券 ****
/ 受贈益 ****
- 売主 1) 低額譲渡(「時価」の1/2未満)の場合
- ○ 法人 → 法人
- 売主 「時価」と「対価」の差額は法人税課税
寄付金 ****
/ 売却益 **** - 買主 「時価」と「対価」の差額は法人税課税
有価証券 ****
/ 受贈益 ****
- 売主 「時価」と「対価」の差額は法人税課税
- 以上の結果、支配力株主が株式を買取る場合、買主が個人の場合には、時価と買取価額の差額に贈与税が課せられます。また、買主が法人株主の場合時価と買取価額の差額に法人税が課せられます。
この税法の仕組みが株式の買集めを困難にしているのです。
- <分散株式の対応>
- 以上のように、分散した株式は買い集めることは困難です。従って、買い集めではなく他の方法により株式分散の弊害が除去できないか考える必要があります。
- ○ 従業員持株会
- 株式が分散している場合には、従業員持株会を結成し、従業員株主の退職・死亡による分散を防止し、買取価格のトラブルも防止することが実務的です。
- <持株会のポイント>
- 第三者への持分譲渡禁止
- 議決権の理事長による一括行使
- 退職(死亡を含む)による会員資格喪失時の強制買上
- 規約による、買上価格の事前決定
- ○ 種類株式の活用
- 従業員持株会等が所有する株式を例えば無議決権株式に転換すれば、株式分散の弊害を相当部分回避することができます。この場合、権利の公平を維持するため、同株式に優先配当を受取る権利を付す等の工夫が望まれます。
(3)議決権に応じた株主の権利(株主の権利はおそろしいもの)
一般的に、会社が発行する株式の議決権総数の2/3以上を所有すると安定的な支配権を得たといいます。これは、2/3以上の賛成多数で株主総会の特別決議が可能だからです。
この事は、仮に過半数の議決権を抑えていても、1/3を超える株主が別途にあれば株主総会の特別決議を自由に行えないことを意味し、合併・営業譲渡等の重要事項については他の大株主の同意を得なければ実施できないということになります。
昨今の激しい経営環境においては、従来と異なり営業譲渡・譲受を他人事とは必ずしも言えない状況も想定されます。このような重要な局面において経営者がリーダーシップを発揮するには、是非2/3以上の議決権を支配しておきたいものです。
もし、2/3以上の株式を支配することが困難な場合には、次に過半数の支配力を支配することが望まれます。過半数の議決権があれば、株主総会の普通決議を採決することができます。
(4)株式支配力を高める方法(持株会社の設立)
株式支配力を高めるために一般的に採用されるのが、持株会社の設立です。
後継者個人が事業承継に伴う株式移転に関する株式買取資金、相続税・贈与税納税資金を負担できる額には限界があります。
- 役員報酬の約半分に相当する所得税・住民税負担が発生
- 他者との比較で、役員報酬の増額には限度がある
- 株式購入資金を借入金で調達する場合、借入金支払利息は損金算入でいない
そこで、後継者の代わりに、後継者の出資による持株会社を設立し、同社が株式を購入することで、後継者自身が株式を購入するのと同様の効果をもたらそうとするものです。
持株会社を活用するのは単純な方法ではありますが、支配力を維持しながら株式の世代交代を進めるには有効な対策です。
(5)株式引き継における資金対策(相続税納税資金を負担する方法)
既に述べましたように、経営者の世代交代の際には後継者への株式移転がほとんどの場合付随して発生しますので、会社としては後継者が円満に株式を引き継げるよう資金面での対応を検討する必要があります。
通常経営者の世代交代において会社が資金を負担する方法には次のようなものがあります。
- ① 退任役員への役員退職慰労金支給
- 役員退職慰労金を支給すれば、多額の費用計上、資金流出を伴うことになります。
この負担を単年度にて負うことは、一時の負担が過大となるおそれがありますので、事前に時間をかけて次の準備をしておくことが望まれます。
- ・有税による役員退職給付引当金の計上
- ・役員生命保険の加入
- ② 後継者への役員報酬増額
- 後継者が自社株取得のための株式購入資金、相続税・贈与税納税資金を負担できるようにするため、役員報酬を増額します。その分会社の収益力は圧迫されると共に、従業員の給与を減額しようとする際には、不満が蓄積される懸念もあります。
- ③ 退任役員所有自社株の購入(持株会社)
- 持株会社を設立し、高齢のオーナー所有株式を取得することは後継者の資金負担が軽くなると共に、相続税納税資金の確保、円満な遺産分割等事業承継各面において有用です。
ただし、持株会社の資金調達能力等に慎重な配慮が必要となります。 - ④ 退任役員所有自社株の購入(自己株式)
- 株式を購入可能な充分な財務体質を有する持株会社が無い場合、オーナー経営者から金庫株として自己株式を取得する案も考えられます。
金庫株の取得においては、法律面・税務面に多面的な検討が必要です。
このように、事業承継は結果として会社の財務体質等に大きな影響を与えるものですので、会社としても長期に分割して負担を吸収できるように計画的な対応が必要となります。

 0798-33-1131
0798-33-1131